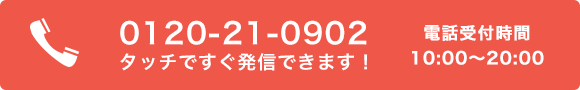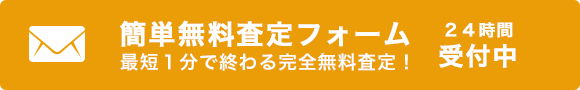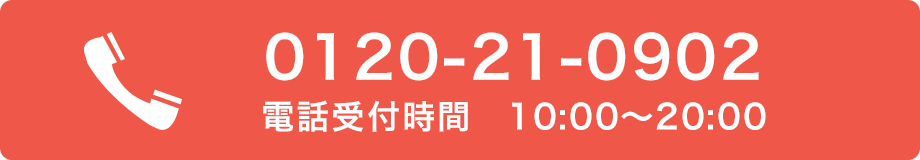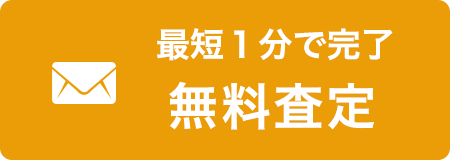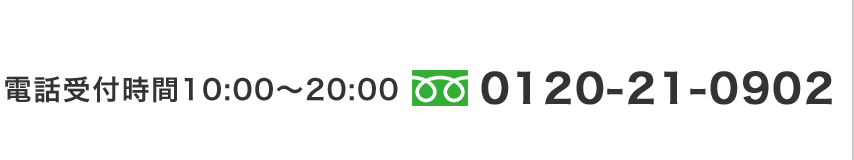注目されている日本ワイン

ワインといえば、フランスやイタリア、ドイツ、スペインなどのオールドワールドと呼ばれているヨーロッパの産地が有名です。
また、1970年代から頭角を現したアメリカ・カリフォルニアを発端に、アルゼンチン、オーストリア、チリ、ニュージーランドなどのニューワールドと呼ばれるワイン産地も注目を浴びています。
しかし、近年美味しいワインはこういった有名地域でなければ造れないという常識は覆されており、新たなワイン産地が世界中で注目を集めています。
そんな、全く新たなワイン産地のひとつとして注目されているのが、我が国「日本」なのです。
世界の有名ワインと比肩するようなワインをはじめ、高品質なワインが日本国内で多く生産され始めています。今後、日本ワインはより話題となり、今以上に注目される存在となるでしょう。
今回、日本ワインを知るために、日本ワインの歴史をおさらいしてみます。ぜひ、参考にしてみてください。
日本とブドウ

ワインを造るために必要な原材料は言わずもがな、ブドウです。
海外では紀元前よりブドウが栽培されており、すでに紀元前4000~6000年にはワイン造りが行われていたともいわれています。翻って日本国内では、奈良時代頃にブドウを栽培していたという説があります。
それ以前、縄文時代にブドウが栽培されていたともいわれていますが、比定的な意見が多いようです。
話しを戻しますが、奈良時代に発見された絵柄から数多くブドウの形をモチーフとしたものが発掘されています。この頃、または以前より日本人はブドウを知っていたと思われます。
日本の固有品種甲州について

日本ワインを世界的に知らしめた立役者は、日本固有の品種『甲州』です。甲州は白ワインを造る白ブドウですが、色が灰色であることからも、グリと呼ばれるブドウです。
ルーツは、奈良時代から平安時代かけてシルクロード経由で入ってきたといわれています。
この甲州には二つの伝来説があり、ひとつは718年に行基という僧侶が持ち帰り山梨県勝沼の大善寺にある薬草園で栽培した説。

また、それから400年ほど後に雨宮勘解由という人物がたまたま山梨県勝沼町の道端で自生する甲州を拾い、自宅で育てたという説です。
まだ、はっきりとは分かっていませんが、甲州の歴史が山梨県勝沼からスタートしたことに間違いはないようです。
はじめての輸入ワインとは?

さて、甲州種が伝来したとしても、日本人にはワイン造りのノウハウはありません。そのため、室町時代までは、ブドウは日本人にとっては生食用だったようです。
ワインの歴史を紐解くと、海外には安心して飲める水が少なかったこともあり、ワインが唯一安心して飲める水分だったため発展したともいわれています。
美味しく安全な水が豊富な日本において、わざわざワインを造る必要性は無かったともいわれているのです。
さて、日本人がはじめて本格ワインに触れたのは、室町時代後期といわれています。1483年にポルトガルから持ち込まれた「チンタ」というワインを飲んだという記述が文献に残されているのです。

ポルトガルやスペインでは、赤ワインをティンタと呼んでいることからも、赤ワインが当時の日本に持ち込まれたと思われます。
その後、ポルトガルから送られたフランシスコ・ザビエルによってポルトガルワインが持ち込まれ、その赤ワインを薩摩大名たちに振る舞ったとされています。
ワインの歴史は、日本の歴史からある意味ではスタートしているのです。
徐々に増えるブドウ産地

それでも、まだ日本でワイン造りが発展するキッカケとはなりませんでした。
しかし、薬用、加工用としてブドウが注目されはじめたことで、1716年ころには3000本以上のブドウ樹が植えられていたとのことです。
また、山梨県勝沼町のブドウは高級品とされており、江戸時代には将軍に献上されていたことでも有名です。
明治時代に発展

日本のワイン造りが大きく動いたのは、江戸時代の末期です。黒船で来航したペリーにより、日本が文明開化の道を歩み出したことがキッカケとなります。
食文化の変化や米を主食して守るために、痩せた土地で栽培ができるブドウを原料としたワイン造りに白羽の矢がたったのです。
1870年には、山梨県甲府市で「ブドウ酒醸造研究所」、1876年には札幌で「開拓史葡萄酒研究所」が設立されるなど、国産ワインが数多く生み出されることとなります。
大日本山梨葡萄酒会社
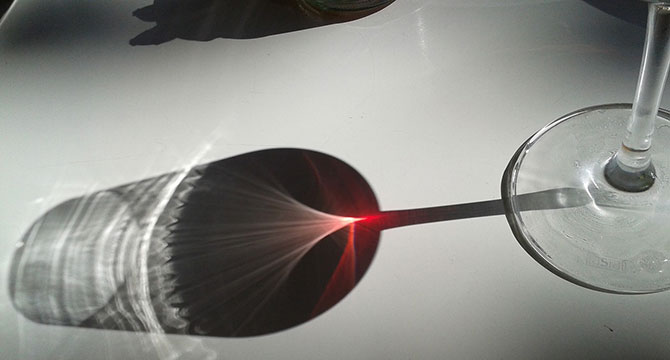
ワイン造りの地盤が日本国内でもできてきたころ、1877年に山梨県に大日本山梨葡萄酒会社が誕生します。
この場所は、後のメルシャンとなる会社であり、日本ワインの発展に大きく寄与する存在となります。
二人の若者をフランスへワイン留学させ、2年後の1879年に本格ワイン造りがスタートしたのです。
混迷の時代、甘口ワインのヒット

本格ワインではなく、甘口ワインがヒットしたことで、日本人がワインを忘れることはありませんでした。
こういった産業としてのワイン造りはもちろん、一方で本格ワインを造る生産者たちも努力を重ねます。
マスカットベーリーAを生み出した日本ワインの父「川上善権兵」や登美農園を買い取り、高品質な本格ワインを生み出すサントリーの前身を築く「鳥井信治郎」などが活躍をしはじめます。
第二次世界大戦が勃発した頃、ワイン産業は壊滅の道を歩むと思われたのですが、ワインに含まれる有機酸の一種である酒石酸が潜水艦などの「音波探知機の振動子」として格好のものであったことからも、ワイナリーの多くが生きながらえます。
終戦後、山梨工業専門学校には、付属発酵研究所という日本ワインの発展のために果実酒専門の研究機関が設置されるなど、日本ワインの発展に多くの人々が尽力したのです。
日本ワインの復活へ

本格ワインではなく、甘口ワインがヒットしたことで、日本人がワインを忘れることはありませんでした。
こういった産業としてのワイン造りはもちろん、一方で本格ワインを造る生産者たちも努力を重ねます。
マスカットベーリーAを生み出した日本ワインの父「川上善権兵」や登美農園を買い取り、高品質な本格ワインを生み出すサントリーの前身を築く「鳥井信治郎」などが活躍をしはじめます。
第二次世界大戦が勃発した頃、ワイン産業は壊滅の道を歩むと思われたのですが、ワインに含まれる有機酸の一種である酒石酸が潜水艦などの「音波探知機の振動子」として格好のものであったことからも、ワイナリーの多くが生きながらえます。
終戦後、山梨工業専門学校には、付属発酵研究所という日本ワインの発展のために果実酒専門の研究機関が設置されるなど、日本ワインの発展に多くの人々が尽力したのです。
ワインブームに湧く日本

明治中期から国産ワインが発展していく一方、輸入ワインにも注目が集まります。
甘口ワインがメインだった日本人ですが、1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万博を期に本格ワインブームが訪れます。
欧米化していく日本の食卓や高度経済成長などの影響を経て、ワイン消費量が国内で増加します。
さらに、1980年代後半にはバブルが訪れたことによる高級ワインブーム、ボジョレー・ヌーヴォーブームなどが重なり、日本ワインは大きく盛り上がります。
近年のワインブーム

1990年代に入ると、チリやオーストリア、カリフォルニアの低価格ならが高品質なワインも注目され、さらに消費量が増えます。
フレンチパラドックスという、赤ワインが心臓病を予防するという学説が発表されたり、日本人がソムリエ世界一となるなど、ワインがより身近に。
これを境に、安定的なワイン需要が日本国内で定着したのです。
今後の日本ワインの行く道は?


古物商許可証取得。酒類販売責任者。
株式会社ストックラボの鑑定責任者、真贋査定士、及び出張買取責任者。 複数の買取会社でウイスキー・ワイン・日本酒・焼酎・ブランデーなどの幅広いお酒の買取鑑定・査定を行ってきた鑑定士歴7年のエグゼクティブバイヤー。